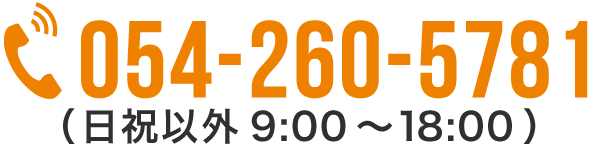
管理者向け評価者研修
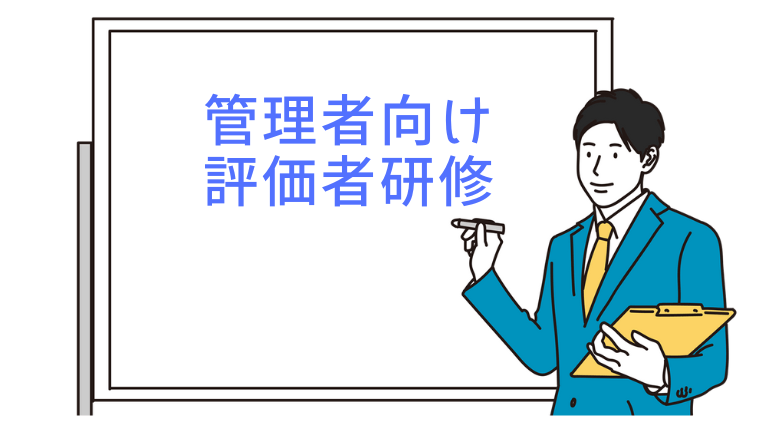
評価者研修とは
評価者研修とは、人事評価を行う評価者に向けて実施する研修です。
評価者となる人材が、人事評価制度の仕組みや評価方法、評価基準などに理解を深め、評価スキルを向上させるために行うトレーニング・演習のことです。評価者スキルの向上は公平な評価を行う上で重要であると認識されています。
もくじ
1回目の研修では、人を評価する難しさを知ってもらう
ある企業で、管理者向けの評価者研修を行いました。営業や工程管理を行っている方々で、管理者と監督者合わせて5名が対象です。この企業では、10月から人材育成を最終目的とした評価制度を導入しました。その制度の公平性を担保するために評価者のレベル合わせをするためのものです。
プログラムの流れ
午前中はインプット中心
1)管理監督者の役割とは
2)評価制度の目的と注意点
午後は、事例を扱って、アウトプットを中心
3)事例 その1 ⇒ 数例の事実を評価する
4)事例 その2 ⇒ ある人物を全員で評価する
評価のポイントを認識し、自らが評価する上での注意点に気付かせることを目的として行いました。
評価に現れるのは、その人らしさ
5人全員でいろいろな評価を出し合いましたが、まったく異なる評価でした。改めて、人が人を評価することの難しさと、多岐にわたる着眼点の多さに驚きました。そして、行動や結果に対する価値観の違いが浮き彫りになりました。
また、価値観の違いに大きく影響されるのが、過去の自分の体験によることも今回、分かりました。
初回にしては、いい出来栄えだったと思いますし、今後とも継続していくことこそ大事だと思います。
更に、「評価制度は人材育成のためにある。」この最終目的を外さないよう、支援していくことを忘れないようにします。
フォローとして、2回目の研修実施
1回目から約半年後、同じメンバーに、同じ場所でほぼ同じ内容のカリキュラムで行いました。
なぜ、1年に2回も同じ教育をするのか。
それは、人が人を評価することが大変難しい、ということと上司が部下を正しく評価することが、その企業と社員の発展に結びついていくからです。
受講者もそこを理解してくれているから、モチベーション高く研修会場に集まってくれました。
復習も興味を持てるような工夫を凝らして
すでに、昨年10月から評価期間が始まっていて先月3月で、最初の期間が迫っています。受講者は明日にでも評価を付けることをスタートする状況なので、再度の研修の必要性を認識している状態でした。
でも全く同じ内容ですと、さすがに受講者は飽きてしまうのでこんな工夫をしました。
まず、テキストを絵や表入りにして、見やすくしました。これで、もう一回同じものを読もう、という気になるようにと。更に復習も兼ねて、テキストの重要なキーワード部分を白ぬきにして、言葉を考えさせて、重要性を認識させました。
午前中の流れとしては
1.人事評価とは
2.人事評価の仕組み
3.人事評価の目的
4.人事評価に関わる要因
5.実施上の留意点
6.評価発生時のエラー
というテーマを学んでもらい前半終了。
午後は、実際に彼らが評価するための、部下の行動などの実例を事前に提出してもらい、それを脚色して、みんなで評価し合いレベル合わせを行いました。
実例なので、ケンケンガクガクいろんな意見を戦わせました。
なかにはどうしてもレベル合わせができない事例があり、やはり人が人を評価することの難しさを感じました。
とはいえ、この評価者研修を継続していくことで評価者のレベルが上がって行き、評価の妥当性を一般の社員が認識できるようになる。そして、社内全体の底上げが図れることを目指していく、そんな流れをイメージして伝えています。
